![]()
自然数・素数の積と級数
自然数や素数で代表される数列の積を、分子や分母に使用した級数を作成する。殆どは結果だけを示している。
円周率は奇数で構成される級数のイメージが強いが、自然数を使用した級数は
奇数 π/4=1/1-1/3+1/5-1/7+… と 偶数 (ln 2)/2=1/2-1/4+1/6-1/8+… を組み合わせて作ることができる。
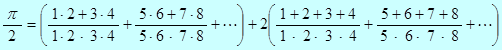
分子が加算だけである級数を作ることもできる。
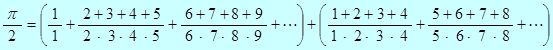
円周率の小数部分を「連続する2つの自然数の積と和の分数」で表した式。
![]()
![]()
(sin-1x)2 の展開で x=1/2 とし、変形すると
π2/18=1/2+1/(2*3*4)+1*2/(3*4*5*6)+1*2*3/(4*5*6*7*8)+1*2*3*4/(5*6*7*8*9*10)+…
ただしこれは 建部賢弘 の式と本質的に等しい式である。
2nの指数も含めて、自然数で構成される円周率の式。
3π =1*2*3*24/(5*6)+1*2*3*4*25/(6*7*8)+1*2*3*4*5*26/(7*8*9*10)+…
π/2 =21/2+1*22/(3*4)+1*2*23/(4*5*6)+1*2*3*24/(5*6*7*8)+1*2*3*4*25/(6*7*8*9*10)+…
![]()
調和級数1/1+1/2+1/3+1/4+… が無限大に発散する事は有名であるが、分母を素因数分解して
'4n+3型素数'(3,7,11,19,23,…)を奇数個含む項を'-'にすると値がπ/2になる。
![]()
上記級数の2倍の値は以下の通り増減する。
2/
1 2.00000…
-2/11 (11)
3.10468…
+2/ 2 (2) 3.00000… -2/12 (2*2*3)
2.93802…
-2/ 3 (3)
2.33333…
+2/13 (13) 3.09186…
+2/ 4 (2*2) 2.83333…
-2/14 (2*7)
2.94901…
+2/ 5 (5) 3.23333… -2/15 (3*5)
2.81567…
-2/ 6 (2*3)
2.90000…
+2/16 (2*2*2*2) 2.94067…
-2/ 7 (7)
2.61428… +2/17
(17) 3.05832…
+2/ 8 (2*2*2) 2.86428…
+2/18 (2*3*3) 3.16943…
+2/ 9 (3*3)
3.08650…
-2/19 (19)
3.06417…
+2/10 (2*5) 3.28650…
+2/20 (2*2*5) 3.16417…
π/2= 1/1+1/2-1/3+1/4+1/5-1/6-1/7+1/8+1/9+1/10-1/11-1/12+1/13-1/14-1/15+… から
π/4= 1/1 -1/3 +1/5 -1/7 +1/9 -1/11 +1/13 -1/15+… を引けば
π/4= 1/2 +1/4 -1/6 +1/8 +1/10 -1/12 -1/14 +… であり
π/4=(1/1+1/2-1/3+1/4+1/5-1/6-1/7+…)/2 と変形すると最初の式に戻る。
この級数は π/4=1/1-1/3+1/5-1/7+… とその1/2,1/4,1/8,… 倍の級数に分解できる。
(π/4)/1= 1/1 -1/3 +1/5 -1/7 +1/9 -1/11 +1/13 -1/15+…
(π/4)/2= 1/2 -1/6 +1/10 -1/14 +…
(π/4)/4= 1/4 -1/12 +…
(π/4)/8= 1/8 -…
:
'4n+3型素数'同士の積は'4n+1型奇数'になる為、
'4n+1型奇数'は'4n+3型素数'を偶数個(0個も含む)持ち、'4n+3型奇数'は'4n+3型素数'を奇数個持つ。
そのため奇数が持つ'4n+3型素数'の個数は偶数と奇数を繰り返す。
4n+1 4n+1 4n+3 4n+3 4n+1 4n+3
1 3 3
5 5 7 7
9 3,3 11 11
13 13 15 5 3
17 17 19 19
21 3,7 23 23
25 5,5 27 3,3,3
'4n+1型素数'(5,13,17,29,37,…)を奇数個含む項を'-'にすると値がπになる。
![]()
![]()
オイラーの定数(γ=0.5772156649…)を自然数で表すと、分子がnである項が 2n-1 個連続する次式となる(Vaccaの式を使用)。
![]()
Nielsenの式 γ=1-1/(3*4)-2/(5*6)-2/(7*8)-3/(9*10)- … -4/(17*18)- … を利用すれば
![]()
![]()
参考:γと ln 2 の関係。 ln 2 = 1/1-1/2+1/3-1/4+… の各項に ln (√2/k) を掛けた形で
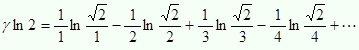
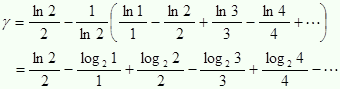
Vaccaの式は分子が整数である。
![]()
![]()
分母が連続する自然数の積、つまり階乗の場合は代表的な式
e=1/0!+1/1!+1/2!+1/3!+1/4!+… , 1/e=1/0!-1/1!+1/2!-1/3!+1/4!-… がある。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1/e の分母や分子は数字がeの場合の逆になっている。e を3の倍数で表現すると
![]()
![]()
分子が階乗の2乗である級数の例は
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ある数列の積を分母に持つ級数を考える。「連分数展開 その他の関数の展開」を参照。
![]() (-1=<1/x)
(-1=<1/x)
![]() (-1=<x)
(-1=<x)
等の式を利用する。
2k番目のリュカ数(L2=12+2=3,L4=32-2=7,L8=72-2=47,L16=472-2=2207,…)の積の場合。
最初の式で 4x+2=3 (x=1/4) のケースは √5=1+4/2-4/(2L2)-4/(2L2L4)-…
つまり 1/L2+1/(L2L4)+…=(3-√5)/2=1/φ2
1/φ2=1/L2+1/(L2L4)+1/(L2L4L8)+1/(L2L4L8L16)+… =1/F4+1/F8+1/F16+1/F32+…
従って黄金比に関する既知の次式を得ることができる。
φ=1/F1+1/F2-1/F4-1/F8-1/F16-1/F32-… =1+1-1/3-1/21-1/987-1/2178309-…
ただし上記の Fn はフィボナッチ数である。
このフィボナッチ数を途中まで使用する場合は、続きの分子をカタラン数にすればよい。
φ=1+1-1/3-1/(3*7)-1/(3*73)-2/(3*75)-5/(3*77)-14/(3*79)-42/(3*711)-…
φ=1+1-1/3-1/21-1/(21*47)-1/(21*473)-2/(21*475)-5/(21*477)-14/(21*479)-…
その性質は次式に由来している。
![]()
F:1,1,2,3, 5, 8,13,21,34, 55, 89,144,233,377, 610, 987,…
L:1,3,4,7,11,18,29,47,76,123,199,322,521,843,1364,2207,…
分母が全て2で構成される級数。
√2=1+1/2-1/{2(22+2)}-1/{2(22+2)((22+2)2-2)}-1/{2(22+2)((22+2)2-2)(((22+2)2-2)2-2)}-…
=1+1/2-1/(2*6)-1/(2*6*34)-1/(2*6*34*1154)-… 22+2=6, 62-2=34, 342-2=1154
=1+1/Q1-1/(Q1Q2)-1/(Q1Q2Q4)-1/(Q1Q2Q4Q8)-…
ここで Qm=round( (1+√2)m ) である。例えば (1+√2)8=1153.9991… であるので Q8=1154 となる。
1+1/2-1/12-1/408-1/470832 = 1.41421356237468…
分母は Q1Q2Q4…Qm=round( (1+√2)2m/(2√2) ) であり、Q1Q2Q4Q8は(1+√2)16/(2√2)=470832.00000026… から値を得ることができる。これはペル数(Pell number)と呼ばれる数列の一部である。
P0 = 0, P1 = 1, Pn = 2 Pn-1 + Pn-2 (n>1)
√2=1/P1+1/P2-1/P4-1/P8-1/P16-1/P32-…
P:1,2, 5,12,29, 70,169, 408, 985,2378, 5741,13860,33461, 80782,195025, 470832,…
Q:2,6,14,34,82,198,478,1154,2786,6726,16238,39202,94642,228486,551614,1331714,…
同様な式は √3 では 42-2=14, 142-2=194, …と続く数を用いる。
√3=2-1/4-1/(4*14)-1/(4*14*194)-…=2-1/4-1/56-1/10864-…
この数列 4,14,194,… はメルセンヌ数 2k-1 の素数判定法(Lucas-Lehmer test)で使用されている。また √3 はPepinによるフェルマー数 22^k+1 の素数判定法で使用される数である。この√3 は2のべき乗型の素数(メルセンヌ素数やフェルマー素数)と関係が深いようだ。
{(2+√3)k-(2-√3)k}/(2√3) の数列は 1, 4,15, 56,209, 780, 2911,10864,…
(2+√3)k+(2-√3)k の数列は 4,14,52,194,724,2702,10084,37634,…
√5 では 42+2=18, 182-2=322, …と続く数を用いる。√5=2√(1+1/4) より
√5 =2+1/4-1/(4*18)-1/(4*18*322)-…=2+1/(2*2)-1/(2*2*3*6)-…=2.236067977…
√10 では 62+2=38, 382-2=1442, …と続く数を用いる。√10=3√(1+1/9) より
√10=3+1/6-1/(6*38)-1/(6*38*1442)-…=3+1/6-1/228-1/328776-…=3.162277660…
以上の数列は実2次体の基本単数やペル方程式の解と密接に関係している。
また連分数の項数の半減を繰り返した式を基にしているため、数列の2k番目の値が級数の分母に使用される。そのためか平方根をニュートン法により求めた値と一致するようだ。例えば a0=1,an+1=(an+3/an)/2 による√3 の近似分数は 2, 7/4, 97/56, 18817/10864, … である。
分母がフェルマー数 Fk=22^k+1 の積の場合は
![]()
![]()
類似の式
![]()
![]()
分子が素数、分母が(素数±1)の積とすると
![]()
![]()
分子が素数±1(あるいはその積)、分母を素数の積とすると
![]()
![]()
![]()
1と素数^素数を使用した級数。
![]()
![]()
素数で構成されるその他の級数。「ゼータ関数等の級数・乗積・連分数」を参照。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
素数と同様に奇数や偶数の乗積を級数化すれば
![]()
![]()
奇数の級数を展開すると
π/4=1/12-1/32-1/52-1/72-1/92-1/112-1/132-1/172-1/192-1/232-1/252-1/292
-1/312-1/372-1/412-1/432+1/452-1/472-1/492-1/532-1/592-1/612+1/632- …
となる。分子の値はメビウスの関数と似て -1,0,+1 になると思われる。「異なる奇数の積」への分割方法によって値が決まる。奇数個の積の場合は +1,偶数個の積の場合は -1 として、その合計の値になる。実例は以下の通り。
-1 : 3=1*3 [-1]
0 : 15=1*15 [-1] と 15=1*3*5 [+1]
+1 : 45=1*45 [-1] と 45=1*3*15=1*5*9 [+2] , 1=1 [+1]
105=1*105=1*3*5*7 [-2] と 105=1*3*35=1*5*21=1*7*15 [+3]
黄金比に等しいフィボナッチ数の乗積を級数化すれば
![]()
これは次のような簡単な式に変形できる。
φ=1+1/(1*1)-1/(1*2)+1/(2*3)-1/(3*5)+1/(5*8)-1/(8*13)+…
φ=1+1/(12+1)+1/(32+1)+1/(82+1)+1/(212+1)+1/(552+1)+…
自然数の積つまり階乗を級数化すれば
![]()
![]()
二重階乗の場合は
(2n) !!=2n+(0!!0)2n-1+(2!!2)2n-2+…+(2n-2)!!(2n-2)20
(2n+1)!!=2n+(1!!1)2n-1+(3!!3)2n-2+…+(2n-1)!!(2n-1)20
例えば
4!!=22+(0!!0)21+(2!!2)20 6!!=23+(0!!0)22+(2!!2)21+(4!!4)20
5!!=22+(1!!1)21+(3!!3)20 7!!=23+(1!!1)22+(3!!3)21+(5!!5)20
上記の多くの式は、次の乗積の級数化式を利用している。
![]()
![]()